
動物の愛護PROTECTION
動物の愛護とは、愛情ややさしさを持って対象動物の習性に配慮して取り扱うこと、すなわち動物の習性等に配慮した具体的な飼養行為に理念を加えることにより、動物とのよりよい関係つくりを目指す行為の総称である。
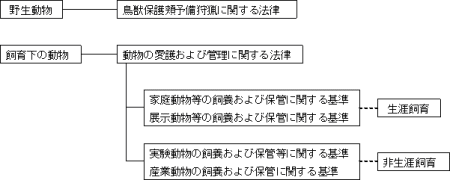
実験動物はペットなどと異なり、原則的に生涯飼育が行われず用途に応じて利用、処分される。実験動物は動物愛護法の規定に基づき、「実験動物の飼養および保管等に関する基準」が定められている。動物愛護法は1999年に大幅な改訂があり、動物の愛護やヒトと動物の共生の理念が盛り込まれ、広く飼育動物を対象とした動物福祉法制の性格が強められた。
わが国における動物実験は、動愛法や実験動物の基準に示される原理・原則に従い、学会や大学等が定める動物実験指針に沿って実施されているが、委員会の設置や実験計画書の審査及び指針の制定が法に明記されていないため、研究機関や研究者個人の責任が曖昧になりやすい点が問題視されている。
わが国における動物の法的な区分
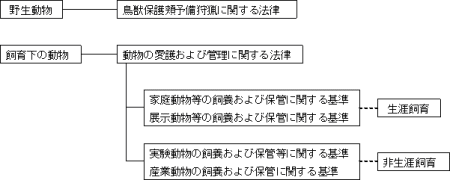
実験動物はペットなどと異なり、原則的に生涯飼育が行われず用途に応じて利用、処分される。実験動物は動物愛護法の規定に基づき、「実験動物の飼養および保管等に関する基準」が定められている。動物愛護法は1999年に大幅な改訂があり、動物の愛護やヒトと動物の共生の理念が盛り込まれ、広く飼育動物を対象とした動物福祉法制の性格が強められた。
動愛法第2条(基本原則)
「動物が命あるものである事をかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめる事のないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」と規程されている。実験動物も、この基本原則に準拠しなければならないが、その合理的な目的と社会的役割に応じて適正に取り扱い、利用する事で、人と実験動物の共生は可能である。
動愛法第24条(動物を科学上の利用に供する場合の方法および事後処置)
実験動物や施設およびそれらの管理に関わる者の定義、動物の導入に当たっての配慮、動物の健康や安全の保持、実験等の実施上の配慮や終了後の処置、動物やその排泄物による人への危険防止動物の汚物等による生活環境の汚染防止等が規程され、わが国における実験動物の適正な飼育・保管等に関する具体的な基準になっている。
法律・基準と研究内容との関係
これら法律および基準は動物実験の実施に関し苦痛軽減や安楽死等の原則を示しているものの、具体的な実験内容に踏み込むものではない。これは、研究内容を一律に法律で規制することは学術分野における独創的な発想や萌芽的研究を阻害する事になり、学術研究の根幹に関わるためである。したがってわが国では学術研究における研究内容を法的に規制するのではなく、研究者や専門家の組織である学会、大学、研究所等が法の趣旨遵守しつつ、独自の指針やガイドラインで自主自立的な規制のもとで実施すべきであるという理念に立っている。
わが国における実験動物および動物実験に関連した法規・指針
| 種 類 | 名 称 | 制定年 | 主な内容 |
| 法 律 | 動物の愛護および管理に関する法律 | 1999年 | 科学的利用に供する場合の原則 実験動物の基準制定 |
| 省庁告示 | 実験動物の飼養及び保管等に関する基準 | 1980年 | 実験動物の適正な飼養と保管 実験実施上の配慮、実験終了後の処置、危険防止、生活環境の保全など |
| 省庁通知 | 大学等における動物実験の実施に関する基本的考え方について | 1987年 | 大学研究所等における動物実験の適正な実施 動物実験指針と動物実験委員会の整備 |
| 学会指針 | 日本実験動物学会ほか | 1987年 | 委員会による実験計画の審査 (科学的妥当性、動物福祉の観点) |
わが国における動物実験は、動愛法や実験動物の基準に示される原理・原則に従い、学会や大学等が定める動物実験指針に沿って実施されているが、委員会の設置や実験計画書の審査及び指針の制定が法に明記されていないため、研究機関や研究者個人の責任が曖昧になりやすい点が問題視されている。